
取締役会議長×社外取締役×YKK社外取締役 座談会
取締役会議長と社外取締役が語る 企業成長に欠かせないガバナンスの実現
YKK AP 取締役会議長 代表取締役会長の堀 秀充、社外取締役の井上 智子氏、YKK社外取締役の小野 桂之介氏が鼎談。YKK APにおける企業成長に欠かせないガバナンスの実現をテーマに語り合いました。
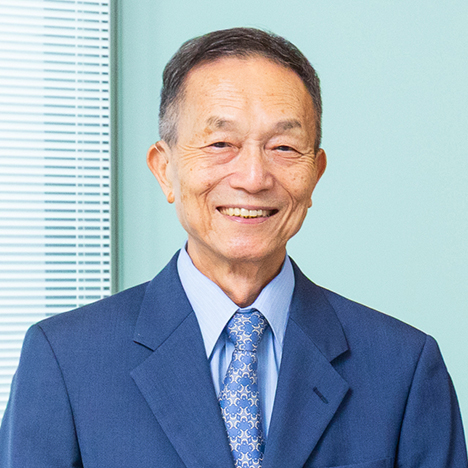
小野 桂之介 氏
慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授、同大学院ビジネススクール校長、中部大学学監、同大学副学長などを歴任。現在は慶応義塾大学名誉教授、中部大学名誉教授。2007年6月よりYKK社外取締役を務める。
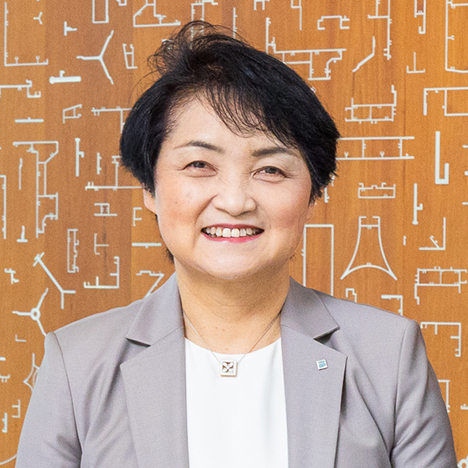
井上 智子 氏
日野自動車工業(現日野自動車)入社後、人事、財務を経験。監査部長、参与兼監査部長、参与兼内部監査領域副領域長を経て、同社常勤監査役に就任。2024年6月よりYKK AP社外取締役を務める。
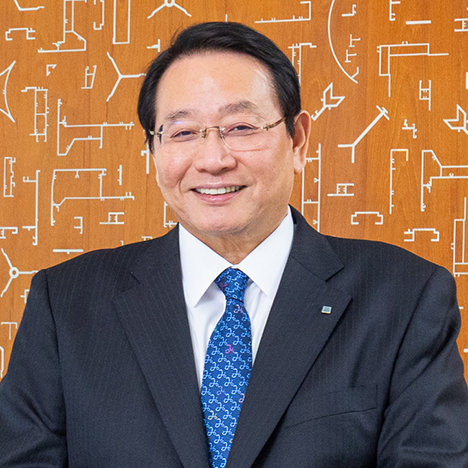
堀 秀充
取締役会議長
1981年吉田工業(現YKK)入社。1989~2006年、米国勤務。帰国後、YKK AP執行役員 経営企画室長、取締役 上席常務 事業本部長などを経て、2011年~2023年3月、代表取締役社長を務める。2023年4月より現職。
初の社外取締役を招聘
多様な視点を取り入れ議論の充実を図る
――非上場のYKK APが社外取締役を招いた理由について教えてください。
近年、経営環境が目まぐるしく変わる中、「YKK APはこのままで良いのか」と不安を感じたからです。2009年、私が事業本部長に就任するにあたり、ここにいらっしゃる小野取締役から「トップシェアを取りプライスリーダーになりなさい」とアドバイスをいただき、迷いなくまい進することができました。実際に業界をけん引する会社となり、会社の規模も大きくなりましたが、当時と現在では状況が大きく異なります。国内市場は、飽和状態で新設住宅着工戸数も右肩下がりの中、資材価格の高騰の影響もあり利益がほとんど出ていません。経営の必要条件もますます増えていく中で、新たな方向性を見いだすためには、外部の方の知見が必要だと考えました。
――2024年6月、YKK AP初の社外取締役として井上智子氏を迎えました。
井上取締役は製造業に精通しており、監査のご経験も豊富です。YKK APが内部統制を強化していく上で、的確なアドバイスをいただける点も選任のポイントとなりました。初の社外取締役を迎え、取締役会に多様な視点が加わったと感じています。
ありがとうございます。商用車メーカーに42年間勤務し、人事、財務、内部監査などを担当してきました。キャリアを重ねる中で感じたのが、机上で絵を描くことは簡単でも、現実の運用に当てはめるのは難しいということです。YKK APの取締役会では、できるだけ具体的に現場の判断根拠や業務プロセスを考えながら意見をお伝えするよう心掛けています。

私は、2007年からYKKの社外取締役を務めていますが、YKKでは社外取締役・社外監査役からの発言がとても活発に行われています。それら外部の声にしっかり耳を傾けるという組織風土があると感じています。これはYKK APにも通ずると思います。社外取締役の意見を取り入れることで、さらなる成長を遂げられるはずだと期待しています。
――小野取締役は2008年に設置された「YKK指名・報酬委員会」の委員も兼任されています。
「YKK指名・報酬委員会」は、YKKとYKK APの取締役、監査役、執行役員、専門役員の人事、および役員の報酬制度設計を主な役割とする、取締役会の諮問組織です。非上場会社で指名・報酬委員会を設置している企業は多くないかもしれません。YKK APの創業者でもある吉田忠裕相談役が掲げた経営理念の中心に「公正」があり、社員の評価制度でも「フェアネス」を行動基準に入れています。非上場だからこそ、なおさら公正に決定し、そのプロセスにも透明性を持たせるべきだという考えがグループに根付いています。YKK AP独自の委員会を設けていないのは、グループ全体で同じ目線に立ち、ガバナンスを有効にするという意図からです。
「社外の目」で改善点を洗い出し
取締役会では討議を尽くす
――井上取締役は、人事、監査のご経験から、取締役会ではどのような点に着目されていますか。
私は、人の能力は気持ちに大きく左右されると考えています。人事においては、「社員やステークホルダーがどう感じるか」ということを重視しています。
また、人が間違いを犯してしまうのは、心が弱っている時に、そうする機会があることによると考えています。そして、そのような機会を与えないようにすることは会社の責任です。従って、監査においては、「業務プロセスにおける内部統制の仕組みに不十分な点はないか」ということを重視しています。
昨年度、井上取締役から不正事案に関する基準や規程の有無について確認されたのですが、YKK APはこれらが十分ではなかったと考えています。出来心を防ぐ仕組みが欠けていたと痛感しています。
大きな組織では、基準や規程を整備することが間違いの抑止につながります。不幸な社員をつくらないことも取締役会の責任だと思います。
――取締役会としての機能を強化するため、運営を見直していると聞きました。
以前の取締役会では、報告と決議を同日に行うことがほとんどでしたが、「討議こそが重要であり、監査役は討議の過程を見ている」という社外監査役からの助言を受け、2023年度からは討議の時間を確保しています。
大きな案件であれば、取締役会で確実に2回は討議を行い、3回目で決議していますね。討議での意見交換は非常に活発で、私もたくさんの質問をさせていただいています。
社外監査役の方々からは、決議に向けて何に着目し、何を準備すべきかといった“お作法”も教えていただきました。井上取締役からも、度々追加の資料を求められたり、質問を受けたりすることがありました。討議時間を十分に確保することが改めて重要だと気づかされ、社内取締役の意識も徐々に変わっていると感じています。
きちんと手順を踏み、活発な意見が交わされる。やはり、社外の目を入れる効果は大きいと感じます。

何より議題が変わりました。社内取締役だけで会議をしていたときは、営業会議の延長のような議論に終始しがちでした。今は、リスクやコンプライアンスにも目を向けながら、会社にとって何が重要かを考える場に変わりました。上場か非上場かは関係なく、企業が成長する上で、こうしたガバナンス体制とその強化が不可欠だと感じています。
広い視野と長期的な視点を持ち
戦略の精度と取締役会の実効性を向上
――第7次中期経営計画策定においてどのような議論がありましたか。
いまだ昨今の資材価格の高騰に適応できておりませんし、事業領域を広げて人員配置を見直したものの、生産性や効率性の追求はこれからです。利益率が高いリフォーム分野に軸足を移し、付加価値を追求していく方針について、また価格転嫁や新たな地域への進出についても時間をかけて議論を重ねました。
加えて、人への投資も欠かせないという議論もありました。第7次中期経営計画を達成するためにも、社員の能力を高め、モチベーションを維持することは大切です。
――外部の視点から、YKK APの経営をどう感じておられますか。
非常にアグレッシブな経営だと感じています。地域的にも事業的にも適切にリスクテイクし、バリューチェーンを広げています。
私はYKK APはトップシェアを取るだけでなく、圧倒的なトップになるべきだと考えます。競合他社に大きく水をあけてこそ、ベネフィットが利いてきます。YKKのファスニング事業はファスナーの用途を拡大して成長しました。まさに、YKK APも国内でシェアを獲得して海外に進出し、窓だけでなく住宅の関連部材にまで事業範囲を広げている段階。市場を獲得して、お客様の信頼を大切にしていけば、利益はおのずと付いてくるはずです。
仰る通りです。取締役会でも、他社に明確な差をつけたいと話しています。当然ながら、既存事業を守るだけでは先が見えません。今がまさに転換点で、次にどんな手を打つべきかを模索しているところです。

――取締役会としての今後の展望や課題を教えてください。
個々の提案について検討する際に、必ず全体のポートフォリオに立ち戻って考える意識を取締役会の中で共有できれば、より議論が深まると感じています。YKK APは各事業の数字がきちんと整理されているので、ありたい姿と現状を踏まえて、どこにどれくらいの資本を投下すべきかを判断すれば、経営戦略やそれを実現するための人事戦略の精度が上がっていくはずです。実効性のさらなる向上に向けては、一度外部の評価を受けるのも手だと思います。
数多くの企業を見てきましたが、YKKのガバナンスは十分合格点に達しています。ただ、当面の議題に時間が割かれ、中長期について議論する時間が不足していることは課題だと感じています。取締役会自体の在り方や議論の範囲など、外部の専門機関からの実効性評価を通してコーポレートガバナンス強化を図っているところです。YKK APはどうでしょうか。
YKK APも同様に中長期に関しては議論の時間が不足しています。自社のガバナンスの在り方や取締役会での討議事項についても再検討する必要があるでしょう。取締役会の実効性評価も第7次中期に予定していますが、まずは自分たちが広い視野と長期的な視点を持って、改善を図っていきます。
この記事をシェアする
- SNSリンク X X シェアする
- SNSリンク Facebook Facebook シェアする
- SNSリンク LinkedIn LinkedIn シェアする
- SNSリンク LINE LINE シェアする
- コピーする リンクコピー リンクコピー リンクをコピーしました








